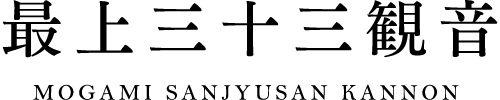最上札所について
最上巡礼事始
光姫物語
最上礼所は、一番若松から始まって、三十三番庭月まで、巡礼の札所は三十三ヶ所ある。それが、いつごろ作られたかは、それぞれの御縁起話に譲るとして、どうして、この三十三ヶ所だけが選ばれたのだろうか。多分、建立の歴史が古いということ、観音さまを祀ってあるからだけではない。それらを結びつける一本の糸がなければならない。その糸が光姫である。
地図を広げてみると、村山市を境界線として、山形市を中心に二十の札所があり、残りの十三は、大石田、尾花沢を中心として散在している。昔は、現在の最上・村山全域を含めて「最上地方」と呼ばれていたし、正平十一年、斯波兼頼がこの地方に封ぜられて、最上姓を名乗るようになったのも、自然の成りゆきであったろう。聖武天皇の天平十三年(約千二百年ほど前)、全国の国府毎に、国分寺が設けられていた。本県ではそれが県内の何処か、まだ確実に分かっていない。しかし、人間が数多く集まって集落を形成すれば、そこに市が立ち、寺が造られる。最上川のほとり、大石田付近が、内陸の中心地であったとみるのは、不自然な考え方ではない。それから六百年経った頃、国分寺が山形市に移されたことは、記録に残っているから、その後、山形市の周辺に寺が建てられていったのではあるまいか。二十の札所が山形市の周りに、十三の札所が大石田の周りに集まっているのは、そのようなことに起因しているのであろう。
輝くように美しい姫ということから、名づけられたのであろう光姫は、斯波兼頼から五代目・頼宗の一人娘といわれる。七歳の春、母を失い、乳母・信夫の手に育てられた。信夫は、根が仏門の出で、姉は成沢村安養寺の尼僧で、安養比丘尼と呼ばれていた。そんな関係で、姫も物心つく頃から仏心が厚く、常に観音経を口にしていたという。天性の美形は、地方の大名たちの噂にのぼり、結婚を望む者も多かったが、頼宗は、京都五条に住む公達を請い受け、姫の婿養子と定めた。名を右衛門佐頼氏といい、二十一歳の器量人であった。この時、姫は十八の秋、まさに好一対の夫婦雛であったと当時の記録は伝えている。その一方、姫への慕情を断ち切れず、悶々とする者もあった。殊に、最上鮭川の領主・横川大膳国景は、姫との婚礼を切望し、再三にわたって頼宗に申し込んだが拒否されていた。姫の結婚後もその恋を忘れることが出来ず、秘かにその略奪の機会を狙っていた。
最初の計画は、翌年の春、頼氏夫妻が平清水の大日如来に参詣する日に実行された。その日は御祭礼で花見の客で混雑していたが、大膳の一味は茶店の者や大黒舞などに変装してこれに紛れ込み、姫に接近しようとした。しかし、荒王重虎などの護衛の侍たちにより、その野望も打ち砕かれた。その乱闘で頼氏は負傷する。
次の機会は、間もなくやってきた。頼氏の傷の養生に、夫婦が高湯に湯治に出た時である。大膳は、城中の重臣山井弾正と姫の召使・小笹を味方に引き入れ、彼らの手引きによって高湯からの帰途を襲った。この情報は、早くも安養比丘尼の手に握られていたが、大膳たちはこれを知らずにかえって逆襲され、大膳はじめ弾正、小笹などの一味はすべて逮捕されてしまう。岩波の乱闘事件である。この時、阪上兵藤が女装して活躍し、安養比丘尼が力を発揮した武勇伝が、見事に描写されている。
執権の氏家重政は、殿の頼宗にその処分を求めたが、頼宗は、大膳は昔からの知人でもあり、その心根がふびんであるからという理由で命を助けようとした。しかし、重臣たちは度重なる暴行に対し同情を寄せる者はなく、遂に打ち首と決定した。頃は卯月の末(今の4月下旬)、大膳をはじめ一味の主な者三名は、馬見ヶ崎の河原で処刑となった。
姫の悲劇は、ここから始まる。
もっと見る
人間の妄執の恐ろしさは、今の人にはわからないほど、昔の人は強く感じていた。大膳が死刑となった後の姫の心には、その出来事が大きな影となって、のしかかってきたのだ。深窓に育った姫にとって、その事件は、たいへんなショックだった。古文書によれば、「城中に大膳の亡霊が現れ、姫を悩ました」とある。自分の非を棚に上げて…と思っても、その悔恨は消すことが出来ない。姫が出家しようと決心した動機は、ここにある。
相談を受けた乳母の信夫は驚いた。いくら思いとどまらせようとしても、姫の決意は動かなかったという。父や夫を捨ててまで、世をのがれ、観世音の霊場を巡礼しようというのである。信夫は、まず姉の安養比丘尼のもとに行くことにした。二人は男に変装すると城をぬけ出した。成沢にたどり着いた時は、夜も明ける頃であった。尼も、何とか止めようとこころみたが、遂に同意せざるを得なかった。それなら、三人で出発すれば心強くもあろうと、旅の支度をすることになる。
数多い観音霊場のうち、どこからまわりはじめたのか、どういう順序にしたのかについては、次のように伝えている。
秋の日の暮れるのは早い。行方のあてもなく歩いているうち、三人は野宿を覚悟した。ふと、山際に燈火がかすかに見えた。その光をたよりに行くと、八十余りになる翁と姥が住む小屋であったという。これも前世の因縁と、二人の老人は三人を招じ入れて接待したところ、三人の話に感動する。老人は、昔は旅の見世物師で、あちらこちらの祭礼に出かけていたため、霊場のことなら知らぬところはないといい、彼女たちに、一番から三十三番までの道筋を詳しく書いてくれた。
温かい一夜の宿の親切で、空腹も満たされ、三人は旅の疲れから、何時とはなしに夢路に入ったが、朝、目を覚ましてみれば小屋はなく、草の中であった。不思議なことに、霊地のことを記した書き物だけが残っていた。これこそ観音さまのお示しであると、三人は西方を礼拝し、巡礼に旅立つことになる。
この旅立ちは秋の初旬と思われるが、三十三番庭月に到着する頃は、秋も終わりに近かった。ほぼ、2ヵ月にわたる道中である。その間、姫の心の内では、父を思い夫を恋うる気持で涙にむせんだ日々もあったろう。しかし、付き添う二人の尼に励まされ、導かれながらの長旅であったに違いない。城中での騒ぎは想像できる。八方手を尽して、姫と乳母の姿を捜し求めたが、僧形に変わっている上に、行動が転々としていたので、遂に発見できなかったのではあるまいか。
庭月の境内に立った姫たちは、大願成就の満足な笑顔に包まれていた。さらに、眼下に見える最上川の流れのほとりこそ、亡き横川大膳のかつての領地ではないか。姫は、彼方にかすむ城跡を眺め、ひざまずいて瞑目するのであった。何の因果か、一時は城を犠牲にして恋に身を滅ぼし、一時は父や夫を捨てて仏門に帰依する。合掌する姫の胸中に去来する感慨はいかなるものであったろうか。
一旦、髪をおろした姫は、念願を果たしたものの、城に戻るというわけにはいかない。今後の住み家を山寺と定めた。この宿に、元・頼宗につかえた身で今は豪農となり、二十人の男女を召し使う身となっていた、菊地式部という者がおり、昔からの顔見知りの安養比丘尼を発見した。それ以来、三人はこの菊地邸に身を寄せることになる。ところが、旅先で気がついたのだが、姫は妊娠していたのである。菊地夫妻の手厚い世話もあって、姫は無事、玉のような男児を産みおとした。これが「若松君」であり、観音霊場一番の名をとったものである。本来ならば、最上家の六代を継ぐ身であったが、母が尼となっているので表に出すことは出来ない。菊地の伜・小太郎の子供として、権三郎という夫婦者に里子に出した。
姫の行方がわからぬまま、八年の歳月は流れる。この間、頼氏はふとした風邪がもとで亡くなり、世継ぎのない頼宗は日夜憂慮の生活を送っていた。
隠しても漏れるのが世の中で、姫らしき人が山寺にいるという噂が流れていた。家中の若侍で執権・氏家刑部の一子・荒王重虎もこれを耳にする。過去、何度も苦い経験を味わったが、万が一と思って山寺をたずねてみた。里人は、姫の身の上を知りながら堅く口を閉じるばかりだった。
重い足を引きずって空しく帰途についた荒王は、ある茶店で足を止めた。見れば、田舎の百姓伜に似つかわしくない品のある顔立ちの子供がいる。よくよく見れば姫君に似ているではないか。そこで権三郎に会って問いただした結果、姫の隠し子・若松君であることが判明する。
荒王と姫の会遇、その後の城中の出来事、姫の身の上話、さらに荒王が殿・頼宗に吉報の早馬となり、事態は一変する。
祖父と孫の対面は、まことに劇的であったろう。迎えの乗り物には、姫、若松君、乳母、尼が乗り、行列を組んで山形に向かった。古文書には「追立て弓台傘、立笠、大鳥毛、対の鎗、鋏箱、殿のお馬はさひ月毛、四つ白、月ひたへ、当世時めく長羽織、振り手の衆がお供なり。・・・・・・」と記して、その見事さをのべている。
この若松君がのちの六代目義春と伝えられている。
光姫の物語は、以上で終わっている。いつの時代、何人によって書かれたかは、もちろんわかっていない。相当古い時代から、言い伝えられ語り継がれてきたことだけは、たしかなことである。三十三観音巡礼は、光姫以前から行なわれていたものとしても、庶民の間から自然に発生し引き継がれてきた、素朴で、熱烈で、崇高な求道の信仰の表現に他ならない。そしてまた、後世も常に平凡な中にも根強く継承されてゆくものに違いあるまい。
| 札所一覧 |